2009年12月1日(火) |
民法の不常識と税務対応 |
不動産取引の危険負担 不動産取引では、売買契約をしてから、実際に土地や建物の引渡しを受けるまでに数週間〜数か月がかかります。 もしこの間に契約した建物が売主買主のどちらにも責任のない原因(類焼や放火)で焼失してしまったとしたらどうなるでしょうか? 誰が損害の責任を取るかということですが、常識的には、契約は解除されるだけ、と思うのではないでしょうか。 すなわち、売主責任です。 危険負担の民法の定め ところが、民法は意外にも、買主責任と規定しています。 たとえ売買対象の建物が無くなってしまっても、買主は売買代金のすべてを支払わなくてはなりません。これに対して、売主は損害賠償も代わりの建物も用意する必要がありません。 買主にとっては怖い規定です。 実際の契約では 民法のこの規定は強行規定ではないので、実際の不動産の売買契約書ではほとんど、常識に合わせて、民法と異なる特約条項を定めるようにしています。 すなわち、引渡しまでは売主、引渡し以降は買主の責任とし、買主に解除権を与えています。
|
税と会計の売買処理時期 会計の売買処理の認識時期の原則は物件の引渡しのときです。 税法も同じ考えで、引渡しのときに売上日、取得日とすることを原則としています。 すなわち、現実の不動産取引の常識多数派の基準と一致しています。 ただし、特約の有無にかかわらず、です。 特約なしの場合は 買主に危険負担がある契約書の場合、物件の引渡しの有無にかかわらず、売主には売却代金が確実に入ってくることになり、買主は確実に物件代金の支払義務を履行しなければなりません。 そうすると、この場合には、契約日を売上日、取得日とすることが理にかなっているようにみえます。 税の例外取扱い そういうことを踏まえて、契約の日を収入計上時期としてもよい、という税務通達があります。 税は民法基準にも歩調を合わせています。 特約があった場合も、です。 |
||
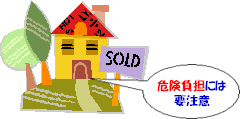 |
|||