2009年4月7日(火) |
相互適用に見る税のあり方
|
神は細部に宿るというが 高齢者世帯の収入は平均的にも、分布で見ても他の年齢層とほとんど変わりがありません。 若い時恵まれていた人は年老いても恵まれ続けているようです。 税の仕組みはどの辺の層を基本において作られているのか、考えてみませんか。 配偶者特別控除の相互適用 年額70万円に満たないような年金しか受け取れないために、共働きをして、それぞれ120万円ほどの収入を得ている夫婦がいたとします。給与所得はそれぞれ55万円です。 それぞれ給与所得が38万円を超えているために、扶養控除としての配偶者控除は適用されません。ただし、76万円未満なので配偶者特別控除の適用は受けられます。 55万円の給与所得の場合は配偶者特別控除の額 21万円 が適用となります。 夫も妻も、それぞれの配偶者を配偶者特別控除の対象として21万円の控除をうけることができるでしょうか。 残念ながらこれは、ダメなのです。法律を作る時に、なぜかこんなケースまで想定しているらしく、ピシャリと排除する規定を置いています。 この人たちは社会保険でも相手を被扶養者にできないし、税法でも頑なな温かくない扱いに遭遇します。 |
配偶者控除の相互適用 少し数字が変わって、それぞれ年額70万円以下の年金収入と年額103万円の給与収入がある共働きをしている夫婦がいたとした場合は、それぞれの所得が38万円以下なのでお互いに相手側の配偶者控除の対象者になる要件を備えています。 もし、双方とも雑損失や居住用財産の譲渡損失や株式の譲渡損失の控除繰り越しの必要などがあることにより確定申告をしておこう、というような場合、自分の基礎控除のほかに配偶者控除の額も記載しておくのはどうでしょうか。 現実に有効に相互適用が機能する場面が想定されないからだと思われますが、配偶者特別控除とは異なり、配偶者控除や扶養親族控除には相互適用排除の規定はありません。 したがって、予備的な意味でそれぞれを控除対象配偶者として記載し合うことには特段の差し障りはありません。 |
||
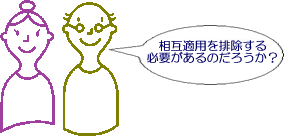 |
|||