2008年7月16日(水) |
なぜ税法は難解不可解 |
三読不可解 税法について、一読半解、二読難解、三読不可解とか、一読難解、二読誤解、三読不可解などと本に書かれています。 しかし、難しいといっても「噸税」も「とん税」と表記するし「棚卸資産」も「たな卸資産」と表記しています。稀覯(きこう)で晦渋(かいじゅう)な漢字を使うのでも、コケ脅かしに外来語をちりばめるのでもないのです。
個々の単語表記は言語明瞭、しかし各条文全体の意味となると難解、不可解といったところなのです。 難しいと思われていない言葉の羅列が理解を妨げる難しい文章を生んでいるのです。 読める漢字と書ける漢字 調査によると、漢字を手で書く機会が減ったと感じている人が93%、手書きでの漢字が書けなくなったと感じる人が85%にも達しています。 しかし、パソコンや携帯電話を使う現代人は、漢字の使用頻度が割合高く、やや難しい漢字も多用しているようです。平がな入力すると漢字変換してくれるからです。書けなくても読めれば漢字を操れるということなのでしょう。 ここからも、通常の漢字使用は「文の難しさ」の原因にはなっていないと言えそうです。
|
意味が違ったら通じない 難漢字より、ふつうの言葉の意味が異なって理解される方が意志疎通を妨げます。 「流れに掉さす」は「傾向に乗りその形勢をより強める行為」の意で、「時流に逆らい抵抗する」の意ではありません。「閑話休題」は「話を脇道から本筋に戻す」の意で、「ちょっと一息」の意ではありません。 税法は難意味派 この例に似て、税法の難解・不可解は知らない言葉の出現ではなく、知っている言葉の熟語化した意味の難解さにあります。 脱線ついでに、次の言葉は間違いですが、正しい言葉に置き換えられますか。 「寸暇を惜しまず働く」「汚名挽回」「例外に漏れず」「負けるとも劣らない」「先立つ不幸をお許しください」「国敗れて山河あり」「濡れ手に泡」「一瞬先は闇」「成せば成る」「全知全能を傾けて」「王候貴族」「具の骨頂」「押しも押されぬ」「役不足ですが頑張ります」「危機一発」「異和感」
|
||
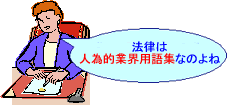 |
|||
|
|||