2008年7月1日(火) |
行政訴訟こそ裁判員制度を |
テレビで初めて 5月25日のテレビ朝日・サンデープロジェクトで、「行政訴訟こそ裁判員制度を!」という特番が組まれました。 行政訴訟にこそ市民の視点を入れるのが裁判の市民参加の理念にも見合うという意見が出されていました。税務は97%敗訴、国家賠償保障裁判ではもっとひどいようで、まったく同感です。 権力の監視こそ 司法は、三権分立の一翼を担っています。司法の最大の使命は、国会と行政を牽制することです。しかし、日本の司法機関にはその自覚がありません。まるで、行政機関の一部、最後の砦として国民と対峙しているのが現状です。 裁判員制度を設けるなら、裁判所を監視し、国会で作られた法律を監視し、行政の行為を監視するためにこそ使われるべきです。特に、国民と日常的に対峙している行政権力こそが現日本の最大の権力機構ですから、これを監視することこそ本筋です。 |
パブリックコメントにもある 公表意見を拾うと、
|
||
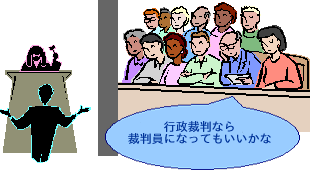 |
|||
|
|||