2007年1月9日(火) |
「和解と税金」その悩ましい判断は? |
「和解」という文言を正確に法律で確認すると、「お互いが譲歩して争いをやめることを約束する契約」となっています(民法695条)。 和解が成立すると、当然それに応じて権利関係も変動しますので、課税関係に十分に配慮しなければなりせん。 通常は、和解契約の内容に従って、課税関係も律せられることになりますが、課税関係をあまり考えずに結果だけを求めた和解をしたため、和解契約の内容が真の法律関係を反映していないと評価されるケースも少なくありません。
事案の内容はこうです。 甲さんが長年居住していた不動産の登記簿上の所有者はXさんでした。 このXさんは、資金に困り、この不動産を売却したいと考え、甲さんに立ち退きを要求しました。 しかし、甲さんは、取得時効を主張したため、話は進展しませんでした。 Xさんも無償での立ち退きは無理と考え、甲さんも取得時効の主張は難しいと考え和解することにしました。 その内容は、時価2億6千万円の不動産を、Xさんが甲さんに支払うべき立退き料を勘案して、1億8千万円で譲渡したことにして、これを甲さんがXさんの指定する第三者乙に2億6千万円で譲渡するものです。 そして、この移転登記と譲渡代金及び双方の取り分の決済が同日におこなわれるものでした。 |
(2)税務署と裁判所の判断 税務署は、甲さんの申告につき、これを短期譲渡所得して更正処分しました。 ただ、甲さん自身も和解の内容を十分に理解していなかったため、裁判所は積極的に救釈明を行使(これには税務署は猛反発しましたが)し、次のように判示しました。 「和解調書の記載の解釈が中心になることは当然であるが、その解釈を行う際には、和解に至った経緯についても十分に考慮に入れた上で当事者の合理的意思を認定する作業を行なうべきである」として、甲さんの所得は、実質的には立退き料であるから、その所得は「一時所得」に該当すると。 これは、税の専門家に相談すべき事案ですね。 |
||
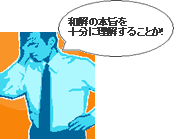 |
|||