2006年12月13日(水) |
信託法84年ぶり抜本改正! |
信託法が84年ぶりに抜本改正となるようです(今国会「第164回」で成立予定)。 現在の信託制度は、イギリスで生まれアメリカで発展した制度を明治の後半に導入してできたもので、明治33年に日本興業銀行法に法律上「信託」という文字がはじめて登場したと言われています。 信託法と言えば、一般的に、金銭や不動産などの所有者(委託者)が、信頼できる相手(受託者)に財産を委ね、自身や第三者(受益者)のために管理や運営を任せる仕組みです。 今回の改正の目玉は、従来の土地や建物、金銭債権などに加え、
などです。 それでは、これらの内容を概観してみましょう。
|
(1)事業信託 この信託は、負債ごとに信託をできることが特徴で、事業の再生や他社との提携などに活用できると言われています。 具体的には、負債を抱える事業部門を事業信託して本体から分離させれば、その事業が失敗しても本体への影響を最小限に食止めることも可能、多額の投資リスクを伴う事業に取組みやすくなります。 これは、自分の財産の管理を第三者ではなく自分に信託するのが特徴です。 身近な例では、親が財産の一部を子供の教育費として「自己信託」した場合、親が自己破産などしても自己信託分は借金返済に充てられず、将来にわたって教育費が確保できることになります。
これは、受遺者に帰属することとなる財産をその受遺者死亡後の帰属先までも指定するものです。 具体的には、遺言で妻を第一次受遺者とし、妻が死亡した場合には、子供や信頼できる第三者を第二次受遺者に指定する遺言信託です。 この信託は、子供のいない夫婦や中小企業の事業承継にその活用が期待されています。 |
||||
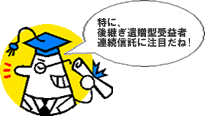 |
|||||