2009年12月4日(金) |
清算所得課税
その計算についての諸説 |
会社が解散した後の法人税の計算は、解散の翌日から清算結了までの「清算所得に対して課税」します。 この清算所得の課税は、法人が解散して清算した場合にまだ課税されていない[資産の含み益]に対して課税することを目的としています。 この清算所得に対する法人税の課税標準は、残余財産の価額から「解散時の資本金等の額と利益積立金額等の合計額」を控除した金額とされています。 次のような算式になります。 残余財産の価額− この残余財産の価額とは、解散時に現存する債権の回収及び財産を処分し、そこから債務の弁済をした後に残った財産です。 そこで、問題は、清算所得を求める際、利益積立金がマイナスの場合(設例参照)、これをどのように処理するかです。 (設例)解散時貸借対照表
|
マイナス利益積立金額をゼロとして計算 上記設例を前提に、残余財産の価額を計算すると「1,500(売却時価)−500(債務)」で1,000となります。 そして、マイナスの利益積立金をゼロとすると、清算所得の金額は、残余財産の価額1,000−(資本金等の額1,000+利益積立金等の額0)でゼロです。これでは、資産の含み益は1,000なのに清算所得の課税がないことになります。 「資本金等の金額と利益積立金額の合計額」を控除する 設例では、資本金1,000と利益積立金△2,000でその合計額は△1,000です。 そして、残余財産1,000からこのマイナス1,000を控除するとマイナスのマイナスでプラスになり、清算所得は2,000となります「残余財産の価額1,000−(資本金1,000+△2,000=−1,000)=2,000」。 資産の含み益が1,000なのに清算所得が2,000では理屈にあいません。 資本金等の金額と利益積立金額を合計し、その値がマイナスの場合はゼロとする この前提で計算すると、清算所得は1,000となります「残余財産の価額1,000−(資本金1,000+△2,000=0)=1,000」。 設例では、たまたま「含み益」と「清算所得」が一致しましたが、この解釈の方が清算所得課税の趣旨に合致しているように思います。 |
||||||||
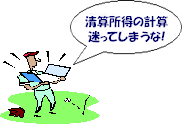 |
|||||||||