2009年5月13日(水) |
損益分岐点売上高を
計算してみましょう |
(1)損益分岐点売上高とは 損益分岐点売上高とは、赤字でもなく黒字でもなく、文字通り損益の収支がトントンとなる売上高のことです。 (2)どのようにして計算するか 損益分岐点売上高を計算するには、まず会社の費用を変動費と固定費に分類します。 費用には、売上高に比例して増減する「変動費」と、売上高の多寡に関係なく定額で生じる「固定費」の2種類があります。 変動費の例:物品販売業における「仕入」固定費の例:「家賃」や従業員の「固定給」 損益分岐点売上高は次の算式で計算できます。 固定費 ÷( 1 − 変動比率 ) (3)計算例 5万円で仕入れた商品を10万円で販売するA社があります。変動費は仕入の5万円だけです。 固定費は、社長の給料40万円と家賃10万円の合計50万円(月額)です。変動比率は5万円÷10万円=0.5です。 |
損益分岐点売上高の算式で計算すると 損益分岐点売上高は、100万円ですので、売上高が100万円を超えれば利益が出て、下回れば赤字ということになります。 A社の諸費用の条件が変わった場合の損益分岐点売上高の変化を見てみましょう。
(4)結論 損益分岐点売上高は低いほど経営が安定しますが、固定費が増加したり変動比率が上がる(粗利が減る)と損益分岐点売上高は上昇します。 損益分岐点売上高を下げるには、「固定費を下げる」「変動比率を下げる(粗利を増やす)」ことが必要です。 過大な設備投資などを行って固定費が増大していると、不況で売上が減少した時に赤字陥りやすくなります。不況に強い会社を作るには、固定費が過剰にならないよう、日頃から注意が必要です。 |
||
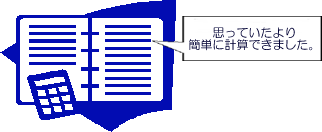 |
|||