2008年11月25日(火) |
振込め詐欺にも雑損控除を |
ネーミングが悪い 「振り込め詐欺」とか「オレオレ詐欺」とか、「詐欺」と名がつくと、被害に対する税法上の扱いは、急にかたくなになってしまいます。 被害救済の雑損控除 被害額を税の負担軽減で救済しようというのが雑損控除ですが、対象となる雑損とは災害・盗難・横領を原因とするものに限られています。 詐欺・恐喝による損失は含まれていません。それで、「振り込め詐欺」も対象外と理解されています。 詐欺・恐喝が税の救済の対象から外れているのは、詐欺や恐喝により相手側に財物を交付させられることの一因が当事者にあるからと解されています。 |
詐欺ではなく横領ではないか? しかし、「振り込め詐欺」の場合は、子供や孫に渡すつもりで振り込んでいるのであり、渡された相手が子や孫ではないのだとしたら、その相手に財物の所有権は移転しません。 ここは通常の詐欺・恐喝と異なるところです。 通常の詐欺・脅迫の場合は、財物を相手に渡す意思をもって、その相手に財物を交付します。 そうすると、「振り込め詐欺」では、犯罪者は振り込まれた金銭に対しては、それを仮に預かっている状態にすぎないわけです。 そして、預かっているものを隠匿・略取することは横領にあたります。 「振り込め詐欺」は、錯誤を誘発して横領できる条件を作り出す犯罪として理解することができます。 なぜ雑損控除がある? また、雑損控除を設ける理由の中には、個人の自力救済・自力報復を禁止する社会制度が選択されていて、その裏側に個人の社会生活上の安全平穏の保障が国家の義務であるということから、国家として予防しきれなかった犯罪による被害については国家責任としての被害補てんをいささかなりともするべき、という考えがあるとの理解をしてもよいように思われます。 そうであるなら、病んだ社会が生み出す新しい犯罪類型により高齢年金者が狙われることに対し、税による救済の配慮は一歩踏み込んで、もっと寛容であってもよいのではないでしょうか。 |
||
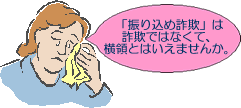 |