2008年10月29日(水) |
家族に優しい税制を! |
義務付けの意味は? 民法では、直系血族及び兄弟姉妹に相互の扶養義務を課しており、場合によってはその範囲は3親等内の血族にまで拡張される、としています。 こういう相互の助け合いがあるべき姿だからこの規定がある、と読みたいところですが、厄介者を国や自治体に押し付けないで、親族で面倒みろ、という姿勢がこの規定を置いているように見えます。 なぜなら、あるべき姿なら、それを助長する方向での制度的支援があるはずですが、制度はその逆ばかりだからです。 親族に支払う必要経費 所得税法では、親族間で支払った経費は、特別な手続をした場合を除き、原則として必要経費として認めていません。 家族は助け合うのが当たり前だろう、という考えが、それを抑制する方向に作用する逆の規定になっているのです。 療養上の世話の対価 療養上の世話を受けるため家政婦などに支払う謝礼は、医療費控除の対象となります。しかし、親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。 ここでも、逆作用しています。 |
年金制度中心社会の本質 老後生活費も、介護も、生活扶助も本来は家族の助け合いを基本に置くべきことなのだと思います。 しかし、諸制度は脱家族を促進する役割をしていて、社会はぐんぐんそういう方向に進化しています。 老人になったら、自分の育てた子供に面倒を見てもらうのではなく、他人の子供の支払う年金保険料で老後の年金生活、動けなくなってからの介護も他人の負担する介護保険で、といった制度になっています。 自分のリスクをカバーしてくれるのが、家族・親族であるからこそ、人類は自分の子供を作り、子育ての苦労を負担し、親族とのつながりを大切にしてきたのに、現代の社会はそれを超克しようとしてきました。 自然を克服しすぎないこと 社会制度のあり方が人工的すぎる、と少子化や子育て放棄という現象を生みます。 他人への支払いは優遇し、家族への支払いは無視するような制度も、ここまで家族制度が危機に瀕してくると、危機を助長する役割を果たすことになってしまいます。 |
||
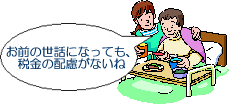 |
|||
|
|||