2008年8月28日(木) |
借名預金と言われて |
相続税の税務調査 相続税の調査では、相続人名義の預貯金が、亡くなった被相続人のものではないかとの指摘を受けることがよくあります。 そんな裁決事例が最近公表されました。 納税者の主張 納税者の主張はよく聞くセリフです。 妻は婚姻後、被相続人了解のもと生活費をやりくりして紡ぎ出したヘソクリを貯め、自らの能力で運用等を行っていたのだから、妻に帰属する財産である。 子名義の預貯金は、子供の頃のお年玉や親戚からの祝儀等と、社会人となった後毎月、生活費として家計に入れていた金員が原資であるから、子に帰属する財産である。 税務署の主張 税務署の主張もよく聞くセリフです。 被相続人が記載した名義人ごとの預貯金残高表の記録をみると、被相続人の日記帳の筆跡と同一であり、被相続人が預貯金全体を掌握し、支配下に置いていたと判断するのが相当である。 子名義の預貯金には、被相続人の退職手当を原資として形成されたと考えられるものや被相続人の筆跡により預け入れられたものがあり、被相続人の預貯金と子の預貯金相互間で名義書換や同一日に取引している事実もある。 被相続人からの贈与との主張も、贈与の意思の証明が不明であり、贈与税の申告書を提出した事実もない。 |
国税不服審判所の判断 審判所の裁決も定番ものでした。 妻は婚姻時に持参金がない上、夫婦間において、家庭生活を妻に委任し、その費用を妻に渡すことや一定の預貯金の管理運用を妻に任せることはあり得ることであり、その事実をもっていわゆるヘソクリが任された妻の財産になるわけではない。 仮に妻が自らの稼得を、仮に子が家計に入れた資金を、全て預貯金としたとしても、名義預貯金の原資に足らず、不合理な主張といわざるを得ない。 また、贈与税の申告書の提出もしていないのであるから妻子に受贈の意思があったと認めることも出来ない。 学ぶこと あとからケチを付けられるのは気分がよくありません。預金の出し入れは必ず本人筆跡ですること、預貯金管理は筆跡のないパソコンですること、贈与税の申告は毎年110万円ずつ行うこと、など留意点です。
|
||
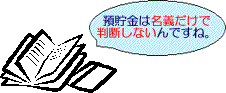 |
|||
|
|||