2008年6月5日(木) |
不利益不遡及の原則 |
租税法律主義 国民は法律の定めるところにより納税の義務を負い、国が課税又は税制改正をするには法律によることを必要とする。 これが、憲法の規定です。 遡及適用は可能か? 憲法は法律による課税を要求しているだけであるから、後から作った法律で遡及課税することを必ずしも禁止しているわけではない、との解釈があります。 素直な日本語文の解釈として、これは正しくないと思いますが、既にここ何十年もの間そういう解釈運営がされてきました。 最近はたてつく人がいる 土地への譲渡課税について「後からの改正税法を遡って適用してよいのか」との問いに今年1月29日福岡地裁は初めて「租税法規不遡及の原則に違反し、違憲無効」との判断を下しました。 その後2月14日 これとは全く逆の相変わらず合憲との判断が東京地裁から出ています。 両方とも高裁で係争中です。 |
歴史的な国会答弁 財務省の加藤治彦主税局長は4月15日の参院財政金融委員会において、民主党の水戸将史議員の質問に答え『税制改正法案が施行日である4月1日を過ぎて成立した場合は「原則として法律は遡って適用されると考えている。 ただし、不利益不遡及の原則があるので不利益な規定は、公布日以降に適用される」と明言した』と報じられました。 不利益不遡及の原則とは 不利益不遡及の原則は、租税法規不遡及の原則とは異なり納税者有利の規定は遡及適用できるとの解釈です。 憲法の素直な解釈としては疑問が残りますが、財務省主税局長のこの発言は先の違憲無効裁判にも重大な影響を及ぼす歴史的な事件です。 当局がかつてこのような見解を表明したことはありませんでした。 日切れの交際費課税はどうなる 日切れの使途秘匿金追加課税制度は4月中支出のものは法律のない状態になります。 日切れの欠損金繰戻還付不適用制度は4月中決算期の会社、交際費課税は4月中開始事業年度の会社には法律不適用です。 しかし、これだと、他の会社との不平等取扱いとなり、別な憲法違反になりそうです。
|
||
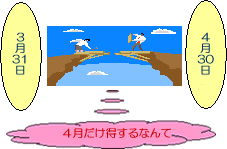 |
|||
|
|||