2007年3月2日(金) |
なりたたなくなった定率法 |
未償却残存価額制度の撤廃、これは平成19年の税制改正での減価償却制度についての画期的な改正です。 償却制度をゆるがす いままでは法定耐用年数経過時点では未償却額がちょうど10%残るように仕組まれていました。これからは、それがゼロになるとのことです。 定率法の償却率は耐用年数をn年とすると、1−(0.1のn乗根)という√を使った算式で求められていました。ここにある0.1というのが未償却残存割合10%の意味なので、残存割合の制度撤廃ということになると、0.1はゼロに置き換えられることになります。そうすると、1−(0のn乗根)という算式になり、答えは常に償却率100%になってしまいます。 制度改正で定率法の償却率算出計算がなりたたなくなったのです。 定額法は無傷で残っている それに対して、定額法の償却率は耐用年数をn年とすると、n分の1という算式で求められていましたので、残存割合の制度撤廃はこの償却率算出計算に影響をもたらしません。 |
いままでもあった未償却残額ゼロのもの なお、いままでも、未償却残存価額がゼロとされていたものが制度上ありました。 無形固定資産がそうでした。従って、無形固定資産には当初から定率法の適用の余地は原理的にありませんでした。 未償却残額ゼロでなく定率法でないもの ところで、未償却残存価額がゼロではないのに、定率法償却の適用が排除されているものがあります。定率法の適用の余地が原理的にはあるにもかかわらず、排除されているものです。 それは生物です。観賞用、興行用などを除き生物については、定額法のみが償却方法とされています。 理由は、未償却残存価額がゼロとか10%とかに固定されておらず、少ないものは5%、多いものは50%とされていてまちまちであり、それぞれの納税者が計算上算出することが大変困難であるにもかかわらず、定率法を適用する時の償却率を税法上提供しているのは残存率10%のケースのみということを踏まえての措置と考えられます。 |
||
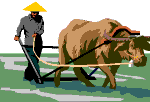 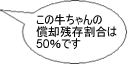 |
|||