2007年2月16日(金) |
特殊支配同族会社役員給与規定存続!! どういう対策をとるか |
修正のうえ存続執行!! 自民党税制改正大綱で、特殊支配同族会社の業務主宰役員の給与に係る損金不算入制度について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる、とされました。 業界新聞でも、「凍結論が急浮上」(「納税通信」2006.11.13)などと書かれたりしたので、もしかしたら、制度廃止もあるのかと期待されていましたが、適用対象範囲の縮小というところに落ち着きました。 でも、3月決算から1年間は800万円基準が存続するのですから、影響の範囲は相変わらず大きいといえます。 第一の対策は適用除外 特殊支配同族会社となるのは、業務主宰役員とその一族が発行済株式総数の90%以上を支配し、かつ、常務従事役員の過半数を占める場合と規定されています。 そして、この特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該法人の事業年度の終了の時の現況で判断します。 したがって、事業年度末までにこの非適用の要件を整えられれば、適用除外になります。
|
第二の対策は影響縮小策 業務主宰役員は一人に限られるという前提があります。これは、普遍性のある話ではありませんが、世代交代期にあるときなどは、給与の分散等により業務主宰役員の給与を低く抑えることで、損金不算入額を小さくすることが考えられます。
複数の会社において、同一人がそれぞれ業務主宰役員に該当するときは、原則としては、それぞれの会社ごとに、給与所得控除額相当分の金額を各別に計算するのですが、それではあまりに損金不算入額が多くなりすぎるので、それらを合算して損金不算入額を求める特例が用意されています。 合算合計給与に対する給与所得控除額をそれぞれの給与に比例的に配分します。 合算対象には、適用除外会社の業務主宰役員給与も含まれるので、こういう給与があるときには、特に損金不算入額の縮小効果は大きくなります。 |
||
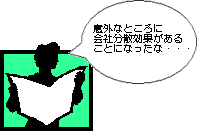 |