2007年2月8日(木) |
被相続人の貸金庫の開扉 |
貸金庫を利用されている大多数の方は、不動産の権利書、遺言書、株券、なかには現金といった重要書類や財産を預けていらっしゃいます。 ちなみに、この貸金庫は、正確には、銀行との契約で、銀行の金庫室の一定区画を対象とする賃貸借契約です。 被相続人の死亡により、当然に、相続人が借主の地位を共有にて相続することになりますが、各相続人が単独で、この貸金庫の開扉を自由にできるかと言えば、そうはいきません。 (1)実務における銀行の対応 相続人の貸金庫開扉請求に対して、多くの銀行は内規等で、被相続人の戸籍謄本、相続人全員が署名した開扉依頼書と全員の印鑑証明書などの提出を求め、これらの提出があって、初めて開扉に応じることを定めています。 これは、一部の相続人による金庫の中身の持ち出しによる、相続人間のトラブルを回避するためです。 したがって、相続人全員の同意があれば何も問題なく開けることができます。 |
(2)一部の相続人よる開扉請求は可能か 法律的には共有にかかる権利の保持のための行為は、一部の共有者でも可能ですが、権利を変更、処分するような行為には相続人全員の同意が必要です。 銀行としては、貸金庫の開扉請求に応じたいのですが、開けて中身を点検、確認するだけの行為であれば問題ないのですが、一部の相続人の開扉は、中身の持ち出しに結びつきやすいため、共有者である相続人全員の同意を求める銀行がやはり多いようです。 (3)開扉のための具体策 全員の同意が得られない場合、相続人としては、銀行に開扉の事情を説明し、中身を持ち出さないことを宣言し、行員立会いもので開扉の交渉をするか、それでも、銀行に受け入れてもらえない場合には、公証人に依頼し、公証人の立会いを条件に開扉交渉をすることになります。 公証人は、開扉事実を公正証書にします。 このことを「事実実験公正証書」と呼ばれています。 |
||
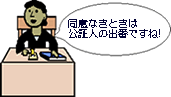 |